どうも。shunです。
私は生活支援員として障がい者支援の仕事に携わって10年ほどになります。
ここ数年で(良いのか悪いのかはさておき)発達障がいという言葉がメディアなどに取り上げられたことがきっかけで、障がいという言葉自体は浸透してきているように感じます。
しかし実際のところ、発達障がいに限らず、知的などの障がいのある人たちが
どんなところで、どんな風に過ごしているのかは知らない方が多いと思います。
実際に私もこの仕事をしていて「障がい者支援って何?」「そういう施設があ
るのは知ってるけど何をしてるの?」みたいな疑問を耳に挟むことがあります。
この記事では、「障がい者施設って何してるの?」という疑問に実際に現場で
働く者としての声を届けることで少しでも障がい者、障がい者施設について理解の一助になればうれしいです。
障がい者施設ってどんなところ?
生産活動や余暇活動って何しているの?
活動内容の一例として生産活動や余暇活動を挙げましたが、私の事業所では具体的には以下のようなことを行っています。
生産活動
- ウエスの作成と納品
- 資源回収
- ペットボトルのラベルむき
- ペットボトルのキャップはずし
- ペットボトルの洗浄
- 缶の選別(アルミとスチール)
- 缶プレス
- 畑仕事
などがあげられます。
余暇活動
- 定期的に外食
- プールや海
- テレビ、DVD
- トランプなどのゲーム
- 各利用者が好きなこと(タブレット、音楽を聴く、クイズなど)
- 散歩(余暇といっていいのか分かりませんが...)
など。
生産活動や余暇活動のどちらにおいてもいえることですが、利用者の方が
取り組める、楽しめることは正直なところそれほど選択肢は多くないです。
それは施設側の環境(職員の体制や余暇道具の不足など)や重度故に道具などを
使って楽しむことが難しい場合があるからです。(もちろん使って楽しむ方もいます)
ただ、そういった環境の中でも支援員の視点として大事なのが「その人(利用者)がどういったスキルや興味関心をもっているのか」をしっかり把握することです。
持っているスキルというと難しく考えがちですが例えば
- タブレットを操作できる
- 順番が理解できる
- 何らかの方法(口頭やカードなど)で意思表示ができる
- 物を持って運ぶことができる
- 物の分別ができる
- 時計が読める
- 分解や組み立てができる(ドライバーなどが使える)
- ある程度の時間、車に乗っていられる
などです。
「え、そんなことでいいの?」という声も聞こえてきそうですがそれらも
その人が持っている立派なスキルです。
物を運ぶことができたり、車に乗っているのが好きであればの、資源回収に参加できるかもしれませんし、言葉がなくても絵カードなどで意思表示ができれば好きなものを選択し行きたいところに行き、食べたいものを食べられるかもしれない、と考えることができます。
支援員(職員)ってなにしてるの?
ひとことで表すのは難しいですが、私の経験上でいうと何でも屋です。笑
それこそ、畑仕事、車の運転、トイレ介助、入浴介助、生産活動や余暇活動の組み立て、
作業に使うための道具を揃えたり作ったり、と本当に多岐にわたります。
基本的には利用者の方のサポートをするのが仕事なので、利用者の方が
ひとりではできないことを補うことになります。
できること、できないことは人によって千差万別のため必要とされるサポート
も変わってきます。
トイレ介助ひとつをとっても、ひとりで行ける人にはサポートは必要ありませんし
トイレの声掛けだけ必要な人、排泄後の後処理が必要な人、すべてに介助が必要な人
もいます。
誰一人として同じ人はいないため、その時、その人に応じた臨機応変な対応が必要になってくる、ということですね。そういった意味で何でも屋です。笑
まとめ
今回は私が働いている生活介護事業所のリアルな様子をお伝えしました。もちろんこれは私の知っている現場であって、法人や事業所ごとに取り組んでいる内容は変わってきます。
この記事を読んで「支援員って大変そうだ」と思われた方もいると思います。
実際大変です。笑
それでもやりがいはありますし、自分が考えたことが利用者の方の役に立った時は達成感もあります。「障がい者施設ってこんなことしてるんだ」「おもしろそうかも」と思って頂ければ幸いです。


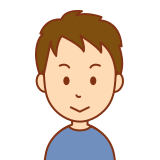

コメント